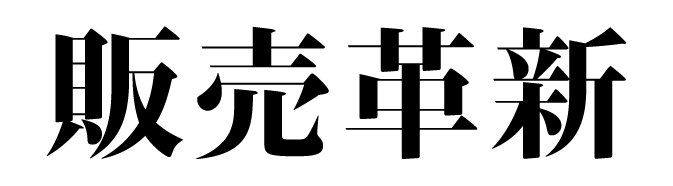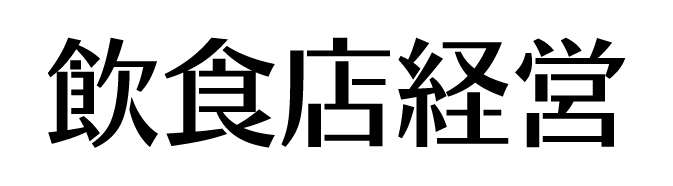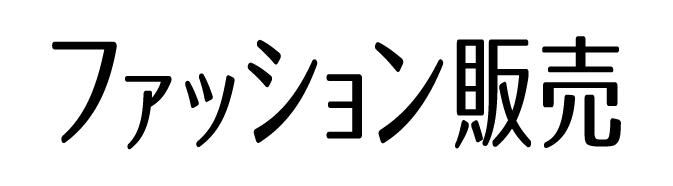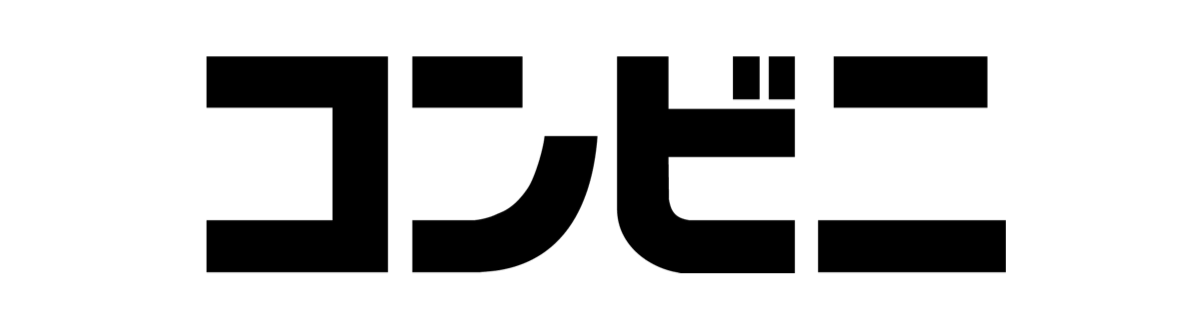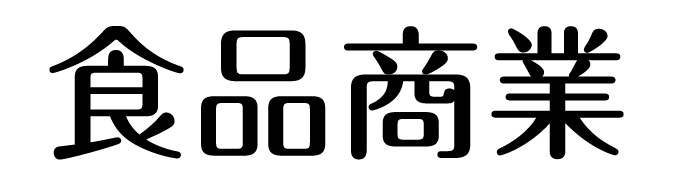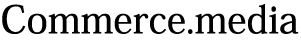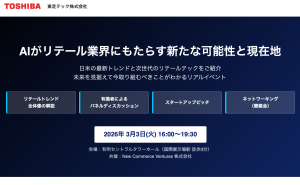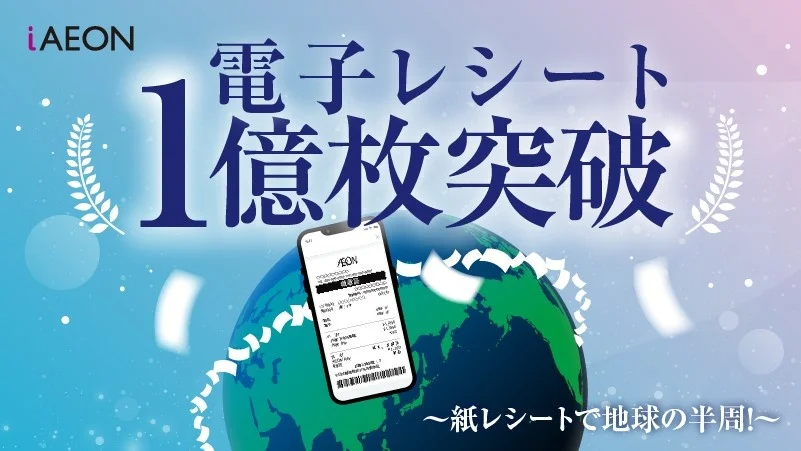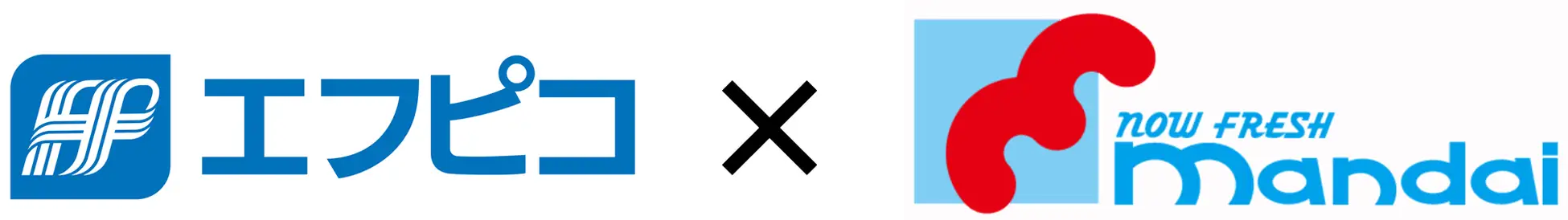ロジカル・サポート代表
三浦美浩
価格、品質、商品で信頼される店の条件
チェーンストア経営には、さまざまなキーワードが存在します。経営幹部から新入社員まで、同じワードを軸に会話を進めています。しかし、実際に、その言葉の意味を問うてみると人それぞれ、自分流の解釈を持って仕事をしていることが分かります。チェーンストア経営で頻出する共通言語を「チェーンストアの“言の葉”」で読者の皆さんと一緒に考えていきましょう。
チェーンストアに「ストアロイヤルティ(store loyalty)」という言葉がある。これは“顧客の店に対する信頼感”のことをいう。お客が慎重に店を選んでいる現状の中で、選ばれる店になるためには、このストアロイヤルティの獲得が重要になってくる。
ではストアロイヤルティはどのように獲得すればいいのだろう?
第一は、お客に“失敗させないこと”である。この要素は売価が典型である。
例えばコロナ禍に毎週、木曜日から日曜日までのチラシ特売を行っているスーパーマーケット(SM)で買物をした。週中の水曜日に食器用洗剤が切れていることに気付き、必需品であり、多くの店を回りたくないので、その店でいつもの商品を298円で買う。
しかし翌日の折り込みチラシを見たら、同じ店で同じ商品が特売価格258円で掲載されている。
お客は「昨日、買って失敗した」と思うのである。
一般的にお客は「価格の安いものを買いたいのではなく、高いものを買わされたくない」のである。特にチラシの短期特価特売が多いSMの場合、お客は大まかな“買いたいチラシ売価”を記憶しており、その売価になると家にない商品を購入する(逆にチラシより高い定番売価では普段は買わない)。
昔は「チラシの特売のときにまとめ買いを……」の購買行動もあったが、少子高齢化でそうした買物は減っている。短期特価特売は"短期"の買物の機会が少なく、消費のサイクルと特売のサイクルが合わない。そのため欲しい価格で購入できず“失敗”は多くなる。
関東エリアのSM企業・オーケーはチラシを店頭配布するが、これは“商品紹介”の位置付けで、あくまで新商品や季節の商品、特別な条件で安く仕入れられた商品を紹介するものである。
掲載された売価は“ハイロー”で上げ下げせず、チラシ期間が終わっても同じ売価で販売を続ける。また競合店対抗価格として、地域の最低売価を保証していて、いつでも安い、同じ価格で買える信頼感は高い。

2024年11月26日、オーケーは関西に進出、スーパーマーケットとしては驚異的な成長を見せている(オーケー高井田店)
売価の失敗を繰り返したお客は、購買行動を“先送り”する。「今、買うと高いのではないか?」「待てば安くなるのではないか?」という気持ちは、日用品の食器用洗剤では買わないわけにはいかないが、洋服の場合は当てはまる。
日本のアパレルは、定番で売れる時期を過ぎると “10%引き”“30%OFF”と続けて、シーズンを終盤には“全品半額”へと進む。お客は“半額にしても儲かる値付け”であることを知っているし、 “30%OFF”で買うと損をすることも知っていて、値付けへの信頼感は薄い。
またシーズン終盤に半額で買っても着る機会も少ないし、来年も同じデザインを着るのは嫌だから、結局、その商品は買わないで終わる(もちろんどうしても欲しい商品ならば購入するが、同じような商品がたくさんあり、いつでもどこでも買えるから買わない)。
ユニクロは、エアリズムなど季節性の高い商品はシーズン最初から、週末のチラシで値引きをするケースが多い。しかもチラシ期間を過ぎると値段は元の売価に戻るので、お客は"今の安いタイミングで買っておこう"と早めの購買を決める。
商品名(素材名)も変わらず、去年も同じ売価で売っていたし、着たことがあるので機能も着心地も分かっているし、早く買った方がシーズンでずっと着られる。店頭在庫も十分にあるので、同じエアリズム素材なら肌着だけでなくポロシャツもまとめて買う。品質だけでなく売価への信頼感も高いのである。

ユニクロはシーズン最初から値引きして、早めの購買を促すケースが多い(24年10月25日にオープンしたユニクロ新宿本店)
前者のアパレルの特売の方法を、チェーンストアの言葉で “売り払い”を示す「クリアランス」というのに対し、後者のユニクロの特売を「セール」「マス化特売」という。後者は大量に普及させるために一時的に売価を下げて、買いやすくする正当な手法である。
一番、目に見えやすい売価は、最も “失敗させてはいけない”ことの一つであり、信頼感を醸成するのに最重要なファクターなのである。
買物行動をがっかりさせる
品質劣化や欲しい商品の欠品
第二に、顧客との信頼感づくりには、 “がっかりさせない”ことが大切だ。“がっかりさせない”ことの一つ目は、最大の要素「品質」である。
例えば家族のいるお客が、とある店で果物を購入したところ、自宅に帰ってみたら、その果物の中身が変色して腐っていたとする。その話を同居する家族に話したら、「あなたがよく見て買ってこなかったからいけない!」と叱られたという。実際の話である。
品質の信頼感の高い店で買った果物ならば、わざわざ電話してクレームを言うだろう。しかしほとんどのお客は面倒なので電話もせず、その店に二度と行かないし、買物もしなくなる。
店にとって問題は、クレームになっていないので“品質に問題がない”となってしまう点である。入荷した商品の段階から問題が発生していたのであれば、商品部やベンダーに対して報告することで、本来の対策を講じることは可能である。
店の段階で劣化など問題が発生したのであれば、保存状態や保存期間を変更したり、陳列前に品質をチェックすることで、問題が再び発生するのを防ぐことができる。しかし信頼されていない店は問題が顕在化せず、目に見えないまま進んでいく。品質で“がっかりさせ”、信頼感を失うケースは減らない。
“がっかりさせない”ことの二つ目は、「欠品」である。気合を入れて買物に行ったのに、欲しい商品がなかったようなケースは、本当にお客をがっかりさせてしまう。
とりわけ1店で、何日分かまとめて購入する買物では、メモなどを持っていくケースが多い。「何かないかしら?」という非計画購買ではなく、「これと、これと、あれ……」という計画購買においては、欠品は"がっかりさせる"要素である。
第三に、ストアロイヤルティをつくるには、まずは“選ばれること”である。
例えば、「今日は夕飯を刺し身にしよう!」と考えたお客が、「今日は○○チェーンに行こう」と想起するようなケースである。こうした、あるカテゴリーを頭に浮かべたら“○○に行こう”などと浮かぶ状態を、「商品によるストアロイヤルティ」という。別の言葉で、こうしたカテゴリーを“目的地”を意味する「デスティネーション・カテゴリー」とも称する。こうしたストアロイヤルティある商品、デスティネーションになるカテゴリーを有するチェーンは強い。
このデスティネーション・カテゴリーは、チェーンストアが狙うべき “365日のうち、300日使う”エブリデー・グッズであり、“8割の人が食べる”エブリボディ・グッズでなくてはならない。
また他社にはないオリジナル商品で、食べ物なら食べ続けられるヘルシーなもの、非食品なら買い続けていっても調和の取れたトータルコーディネートのできる商品でなくてはならない。多くは他社やナショナルブランドにはない、プライベートブランド商品が主力になる。
お客は“ポイント○倍”といった見せかけの販促、瞬間の安さの短期特価特売、声掛け販売などの商略ではなく、本当に安全で安心で信頼できる店を選び始めている。
逆にいえば、お客が価格でも、商品、品質でも、サービスでも信頼できる店、ストアロイヤルティが高い店を求めている今、これに応えられる店になれば、わが店はこれからも強くなっていくはずである。
※「販売革新」2021年7月号掲載誌面を一部加筆し掲載しています
◆ 筆者プロフィール
三浦美浩(みうら よしひろ)
1987年東北大学卒業、損害保険会社勤務を経て㈱商業界入社、「食品商業」編集長、『販売革新』編集長、2011年8月商業界取締役就任、17年1月に独立しロジカル・サポート㈱設立、20年4月にエイジスリテイルサポート研究所所長に就任し現在に至る。