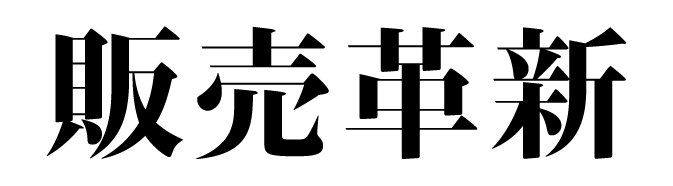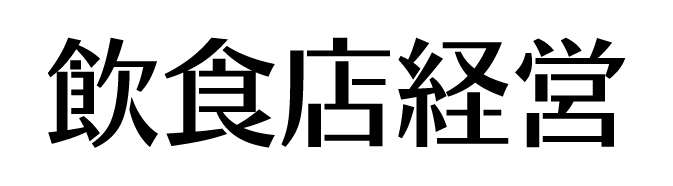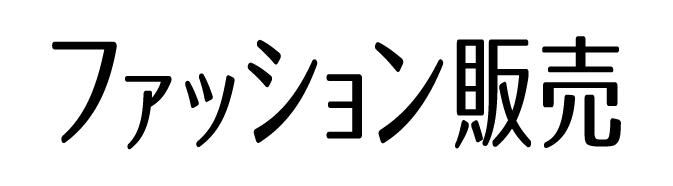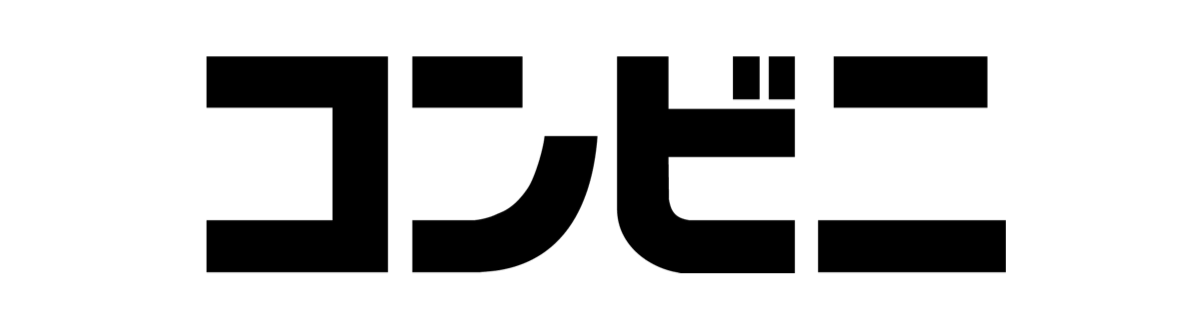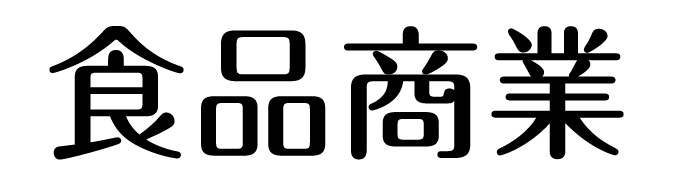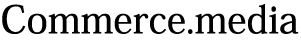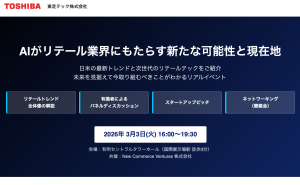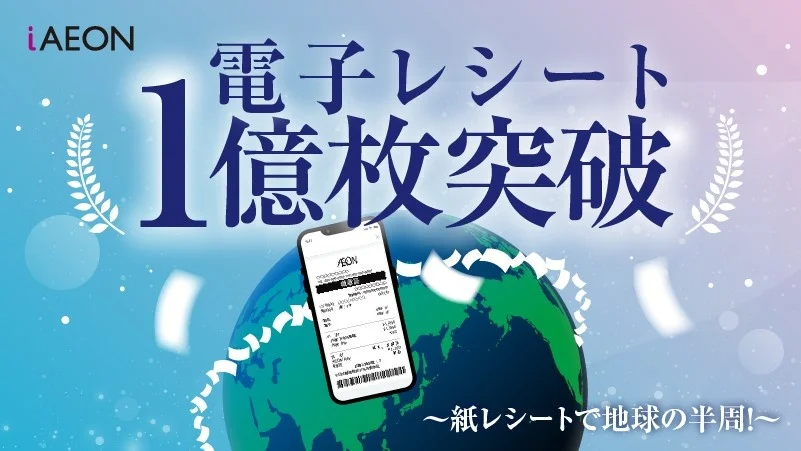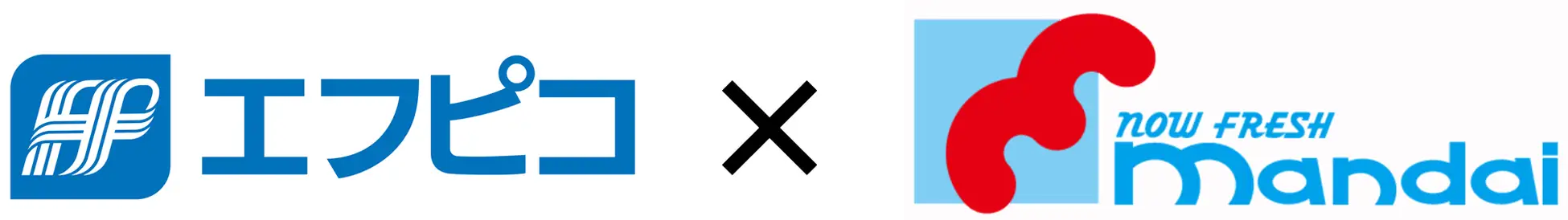ロジカル・サポート代表
三浦美浩
変化を続ければ成長は加速
チェーンストア経営には、さまざまなキーワードが存在します。経営幹部から新入社員まで、同じワードを軸に会話を進めています。しかし、実際に、その言葉の意味を問うてみると人それぞれ、自分流の解釈を持って仕事をしていることが分かります。チェーンストア経営で頻出する共通言語を「チェーンストアの “言の葉”」で読者の皆さんと一緒に考えていきましょう。
行動自粛を意識した生活が長く続いた数年間にニーズが高まったのが “健康の維持”である。その間、多くの人が自粛生活による健康のマイナスを取り返そうと、ランニングなどを始めようと計画した。
テレビで話題になっている近くのワークマンに足を運ぶと、ランニング関係のアイテムがそろっている。プライベートブランドの “Find-Out”の冷感機能を持った「アイスアーマー」のトップス980円(価格は21年6月号掲載時、以下同)、パンツとレギンスが一体になった「(アクションセーブランニング)レギンス」1,780円などである。2点を購入しても税込で合計2,760円である。これ以外にも「アスレシューズ」1,900円、「キャップ」980 円などもある。
まとめて購入すれば色合いも、スタイルもコーディネートしているし、ランニングが長続きするかも分からないから、初心者向けの"エントリーモデル"で十分だろうと、トップスとレギンスを購入する。ワークマンでは初の買物である。

ワークマンの「アイスアーマー」のトップス980円と「(アクションセーブランニング)レギンス」1,780円。2点を購入しても税込で合計2,760円。スポーツ専門店からスポーツウエアをラビンロビングしている
低い価格帯でそろっているので気兼ねなく買えるし、複数買いもしやすい。2点でも、スポーツ専門店に行けばTシャツ1枚も買えない値段である。
ワークマンといえばその店名の通り、1982年に作業服、作業用品の店として設立した専門店で、2024年3月末には1011店舗を数える大チェーンである。今は、そんな店がスポーツウエアを販売する時代なのである。
百貨店から非食品を奪うが
新興勢力に非食品を奪われる
ラインロビングという言葉がある。ここでいう “ライン”とは、ある価格帯に属する商品ラインのことで、"ロビング"というのは “ROB”という「奪う」の意味の英語である。これまでその商品を扱っていなかった業態が、新しく商品を売場に導入し、既存の業態から奪い取っていく様子をいう。
ワークマンの場合、これまでの作業着、作業用品の商品ラインに加え、スポーツ用品などの専門店からスポーツウエアという商品ラインを奪い取ろうという作戦である。そもそもワークマンが扱ってきたワークウエアは、ランニング、キャンプなど“アウトドア・スポーツ”に最適な機能を有している。
ワークウエアのお客は暑さ、寒さの下での作業が多く、また汗をかく作業が多いので吸湿、速乾などの機能が求められる。こういった機能はスポーツウエアにも共通して求められる機能である。
Find-Out ブランドも“スポーツ系ブランドの定価の3分の1を目指して開発”(ワークマンHPより)したもので、まさにスポーツ系ブランドから顧客を奪い取ろうという商品なのである。
考えてみれば、チェーンストアの歴史は “ラインロビング”の歴史である。
江戸時代の呉服商にルーツを持つ百貨店が小売業界の王者だったのが、戦後小売業のスタートだった。そこに"主婦の店"運動に端を発して1957年に創業したダイエーなど、チェーンストアの総合スーパー(GMS)が生まれる。ダイエーは薬品から始まり食品、衣料品、家電などの商品ラインを"ラインロビング"して"総合化"を果たし、72年には百貨店・三越を超え売上高日本一になった。
主婦の店運動などからスタートした一部の企業は、食品と雑貨を中心とする品揃えで地域の市場、八百屋、魚屋、肉屋の業種店からラインロビング、総合化を果たし、スーパーマーケット(SM)企業として成長していった。現存しているSM企業の多くは、こうしたルーツを持つ。
近代的小売業として最初にラインロビングを果敢に行い、総合化、成長していったGMS、SMチェーン。しかし、そうした企業も90年代後半から"ラインロビングされる側"になっていったのが歴史の流れである。
GMS、SM企業の多くが加盟する業界団体・日本チェーンストア協会の統計数値で見ても、98年の加盟社の総販売額(121社・7,247 店 )が16兆8,341 億円をピークに減少を始める。2022年には協会加盟社(56社・1万683店)の総販売額は13兆2,656 億円となり、1998年比で21%の減少となっている。
GMSの非食品分野をラインロビングで奪っていったのが、70年代以降に創業した後発勢力である。
代表は家電のヤマダデンキ(74年設立、83年、本格的チェーン展開開始)、住居関連の専門店・ニトリ(67年、似鳥家具店創業、86年、店名を「ホームファニシング ニトリ」に変更)、紳士服の青山商事(64年設立、74年、業界初の郊外型・紳士服専門店開店)、カジュアルウエアのユニクロ(84年、「ユニクロ」の店名で1号店出店)などである。
専門店の成長に対して、GMSの非食品分野は急速に衰退する。
経済産業省の商業動態統計によれば、“スーパー”(ここには衣食住フルラインのGMSとSMが含まれる)の年間販売額は最盛期の98年12兆5,911億円に対して、2020年は14兆8,112 億円。しかし非食品の個々で見ると衣料品と家電は1998年比で約3分の1、家具に至っては15.0%で6分の1にまで縮小しているのである。
大都市の中心に出店していた百貨店に対し、郊外の駅前立地などを中心に相対的なローコストで出店したGMSは “百貨店ほどは高くなく、何でもそろう店”として成長した。しかし90年代以降、 "モノ不足"の時代は終わり、商品を自由に選べる時代へ社会は成熟していく。
衣料品にしても、ホーム関連にしても"何でもそろう"ことから “欲しいモノが買える”ことをお客は求めてきた。家電、衣料品、食品という、来店頻度も購買頻度も全く違う商品が1店に“そろっている”価値は薄れる。
そうした中で、後発の専門店勢力は駅前も離れ、さらに郊外の住宅地の近隣にもっと低コストで出店する。店も安さ、個性、独自性など細分化が進み、近くで"欲しいモノが買える"専門店を選べる時代となっていった。非食品の販売の主役は専門店勢力へと移っていったのである。
70 年代以降、ラインロビングで百貨店など旧勢力から奪ったGMSは、この20年間にさらに新興の専門店勢力にラインロビングされたのである。
1958 年に米国ハーバード大学のマクネア教授が唱えた「小売りの輪」という理論がある。低コストの新しい小売業者が低価格で市場に参入し、既存業者の売上を奪って成長する。しかし、成熟してくると価格の競争力は小さくなり、品揃えやサービスで付加価値を追求し始め、結果としてこの勢力も高コスト体質になっていく。
するとさらに技術を模倣したり、サービスを革新し、新しい低価格を実現した新規業者が市場に参入、既存の勢力から顧客を奪い新たな成長を遂げていく……そんな考え方である。
まさしくチェーンストアの歴史は、ラインロビングの歴史そのものなのである。
※「販売革新」2021年6月号掲載誌面を一部加筆し掲載しています
◆ 筆者プロフィール
三浦美浩(みうら よしひろ)
1987年東北大学卒業、損害保険会社勤務を経て㈱商業界入社、「食品商業」編集長、『販売革新』編集長、2011年8月商業界取締役就任、17年1月に独立しロジカル・サポート㈱設立、20年4月にエイジスリテイルサポート研究所所長に就任し現在に至る。